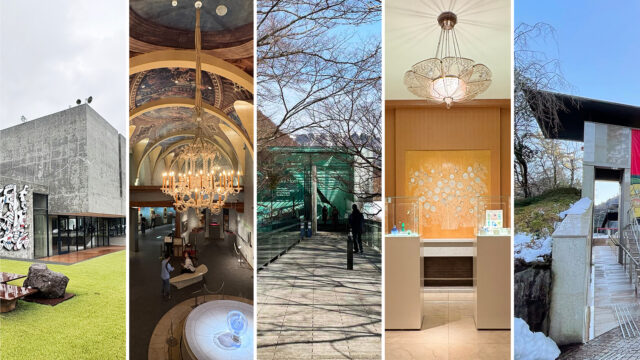神奈川工科大学KAIT広場|緑の丘に埋もれた無柱の大空間

前回の投稿で取り上げた神奈川工科大学KAIT工房の隣に、2020年に完成したKAIT広場。KAIT工房と同じく石上純也設計事務所の設計で、完成前から話題になっていた建築です。KAIT工房と合わせて見学に訪ねてきました。
土地の起伏に埋もれるように建つ低層建築

神奈川工科大学構内のほぼ中央に位置するKAIT広場。起伏のある土地に埋もれるように平屋で建ち、中高層の校舎に囲まれた中で広々とした風景を生んでいました。

地表面からみえている部分の高さは2.5mにも満たなく、一般的な住宅よりも圧倒的に低いスケール。隣接する同じく平屋のKAIT工房やその奥の公園のような広場と合わせ、一体的な空地を形成していました。
柱のない、82m×55mのワンルーム空間

建物高さが低く抑えられ、周囲から眺めると窮屈そうにもみえるKAIT広場も、建物内に入ると印象が一変。建物北側から坂道を下って入ると、約82mx55mの柱のないワンルーム空間がひろがっています。
隣接するKAIT工房の一辺が約45mであることを考えると、このKAIT広場の面積はその2倍以上。それだけの大空間が無柱で実現している姿には、かなりの迫力を感じます。


建物内の天井高は建物全体で共通して約2.4〜2.8m前後。数字だけみると住宅とさほど変わらないようにみえるものの、空間体験としては圧倒的に広々とした印象。おそらくは床面がすり鉢状に傾斜していることで、一般的な建物ではみられない大きな高低差を体感できるからかもしれません。高低差は最大で約5.0mにもなるそう。

大きな高低差があることで、内部空間の端からは屋根に空けられた開口部を通して屋根面を眺めることが可能。内部空間の大部分は周囲の地面よりも低い高さにあることから、側面の窓からは地面に生えた植物を横から眺めることもでき、立っている場が地上なのか地下なのか、よくわからなくなる空間体験でした。
機能をもたない広場という用途、美術館のような

KAIT広場という名前が表すように、そもそもこの建物は明確な機能をもたない建築。内側には造り付けの家具も一切なく、美術館の展示室のような緊張感が。消防法上必要となる消火器も、外壁の厚みをうまく利用して窓の額縁内に納められ、石上さんの意図した空間が可能な限り純粋に体験できるよう配慮された設計。

訪問したときに雨が降っていたこともあるのか、水を扱った内藤礼さんの作品が印象的な西澤立衛さん設計の「豊島美術館」に似た空間の質を感じました。なお、出入口の受付ではヨガマットの貸し出しを行っており、日常的にこの場所でヨガを行っている利用者もいるよう。
気候によって姿を変える建築のありかた

KAIT広場の空間を印象づけている大屋根は、構造リブで補強された薄い鉄板により構成されているよう。同じく鉄板を組み合わせて構成された壁とピン接合で接続され、周囲から中央に向けて大きく垂れ下がるようにつくられています。

端部をピン接合としているのは屋根の鉄板の熱収縮に対応するためだそうで、天井高が最大で30cm程度変動するとのこと。気候によって空間が変化する建築のあり方は、過去の展覧会等で天候に応じて姿を変える建築の構想を発表してきた石上さんならではのように感じました。
薄く仕上げられた屋根とそこから流れる水の繊細さ

内部空間の大部分は鉄板にウレタン塗装を施してそのまま仕上げになっており、壁と屋根は共に必要最低限の薄さに。特に、屋根の開口部の縁は限界まで薄く繊細に仕上げられ、端部で15mmの厚さまで抑えられています。

15mmというと、ほとんど模型のような薄さ。これだけの大空間を覆う屋根全体がこの寸法で実現しているようで、CGを見ているかのような錯覚を覚えます。端部を納めるディテールも建物内からみえることはなく、空を切り取ったかのような開口部の見え方はアメリカの現代美術家、ジェームズ・タレルの作品のよう。

なお、屋根の開口部には建具の類は一切設けられておらず、雨や雪はすべて屋根の内に流れ込む計画。床には構造スラブ等を一切設けずに透水性アスファルト舗装とすることで、基本的にそれらの水は地中に浸透させる排水計画がとられています。

KAIT広場のような抽象的な空間においては、舗装に浸透しきらない雨水がつくる水たまり、それ自体も美しく見えるようでした。安全をみてか、一部に設けられている排水桝がオーバーフローとなる位置に計画されていることからも、水たまりのでき方もある程度コントロールされているのかもしれません。
ー
広場という機能でつくられたこのKAIT広場、雑誌等で設計時の経緯をみると、一時はカフェの機能も検討されていたようです。丹念に検討された繊細なディテールの積み重ねで生まれているこの抽象的な空間が、他の機能と交わったときにどのようになっていたのか、そうした姿も見てみたかったように感じました。
新型コロナウィルス感染症の影響等もあってまだ特段の催し等は開催されていないようでしたが、今後この空間がどのように使われていくのか、将来が楽しみな建築でした。
神奈川工科大学KAIT広場
[所在地]神奈川県厚木市下荻野1030
[主要用途]多目的広場
[設計]石上純也建築設計事務所(建築)、佐藤淳構造設計事務所(構造)
[施工]鹿島建設横浜支店(建築)
[竣工]2020年
[参考図書等] *Amazon商品ページにジャンプします
・『a+u 2023年11月号ー特集:石上純也 最初から現在まで』株式会社エー・アンド・ユー、2023
・『新建築2021年1月号』新建築社、2020
・『ディテール2022年7月号』彰国社、2022